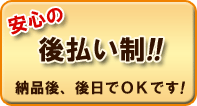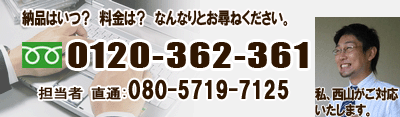よくご依頼をいただく内容のひとつに、ウェブサイトの翻訳があります。
とくに多いケースが、ウェブ制作会社やデザイン会社が、自身のクライアントから依頼を受けて、それを私たちが翻訳する場合です。
皆さんもよくご覧になったことがあると思います。
元々が日本語のウェブサイトで、英文にも対応しているような、そんなサイトですね。
↓こんな感じ


ウェブサイトの文章は、論文や手紙などと比べて、一文ごとの文字数が少ないのが特徴です。箇条書きの箇所なんかも多くあります。
結局、文字数が少ないというのは、情報が少ない、周辺情報もない、という状態ですので、専門用語を知っているかどうか、というお話ではなく、意図していることが分かりづらい場合があります。
もちろん、原文だけでも翻訳は可能ですが、私たちとすれば、「せっかくご利用いただくのですから、しっかりとした原稿を」と思います。
そのため、翻訳過程では、原文を元に、お客様にお電話でのヒアリングを行い、周辺情報をお伺いします。それによって、翻訳時の表現やワーディングの精度を高いものにしていくという手はずです。
といっても、お客様にクライアントがいらっしゃる場合、なかなか「私たちが直接お話を」というのは難しいと思います。(ホントはお伺いできればベストなのですが)
そんなときは、いったん作成過程に入り、翻訳原稿に注書きを入れてお送りします。
その内容をクライアントにお見せいただき、ご評価をいただいて、私どもで修正内容・ご要望を反映していく、という流れを取っています。
同じ文章でも、ワーディングや表現の仕方によって、かなりイメージが違ってきますので、ここは大事にしたいところですし、私たちがウェブサイト翻訳でもっとも注意を払っている部分です。
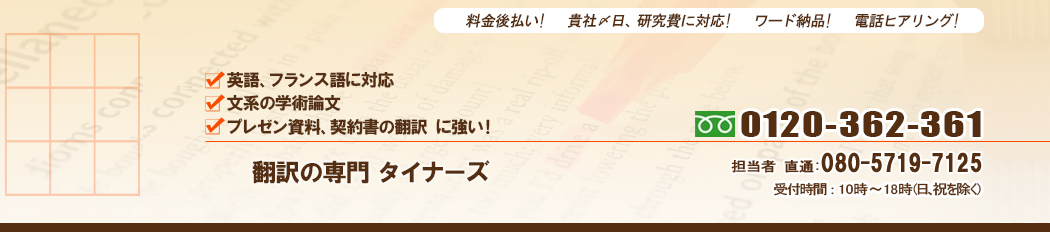 翻訳会社 タイナーズのブログ
翻訳会社 タイナーズのブログ