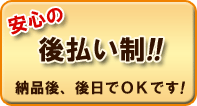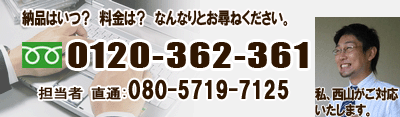数年前に司馬遼太郎さんの「関ヶ原」を知人に勧められ、
初めて歴史小説を読んだら、予想外に面白いしハラハラしたので、
それ以来、戦国時代について調べるのが小さな趣味になっています。
でも、1600年の前後20年ずつくらいなので、
にわか歴女という軽い感じですけれど。
そして、関ヶ原、彦根城あたりを旅行して、
初めて史跡めぐりというものをしました。
それまでは、旅行先に観光スポットとして、
城とか史跡があると、へえ、これが歴史の本に出てきたあれなのか、
くらいの感想だったのですが、「関ヶ原」を読んでからは見かたが変わりました。
戦国時代が、まだ400年しか経ってないことと、
歴史の資料が多く残されているからだと思うのですが、
「関ヶ原」のなかの武将たちは、
生い立ちとか考えかたとか人間臭さを感じて、偉人と言うよりも、
1人の人間として、こういう人がいたんだな、
と思えるようになってきました。
(歴史小説は多少のフィクションはあると思いますけど。)
関ヶ原に行って、小説のなかに出てきた場所が、目の前にあって、
ここで戦があったのか、って思ったら、ふと、
今まで地名と思っていた城や道や古戦場の全部に、理由と歴史があって、
そういうものが繋がって今になっているのが感慨深いです。
史跡巡りをするときは、その時代のことを知っておけば、
もっと楽しくなるのだと思いました。
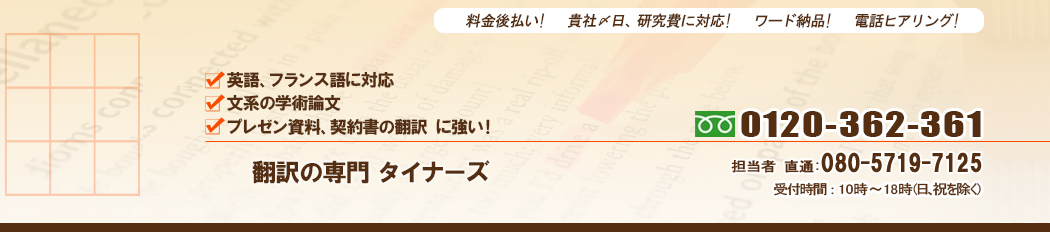 翻訳会社 タイナーズのブログ
翻訳会社 タイナーズのブログ