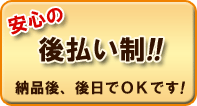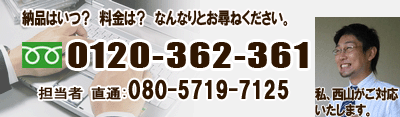早いもので、北京オリンピックからもう4年が経とうとしています。そういえば、2月は29日までのうるう年なので、今年はオリンピック・イヤーなのです。
ロンドンで開催されるオリンピックにむけて、さまざまな競技で代表選手の選考も始まっていますが、競泳でも代表選考会が行われました。
過去数回のオリンピックでは、マラソンの代表選考にあたり、その選考方法や基準をめぐって、議論がかわされ、少々納得できないような代表選考もあったような気がします。
その点、競泳は潔いの一言です。まさに、代表選考会の一発勝負なのです。そして、そこで2位までに入ることと、さらに派遣標準記録とよばれる、非常に高いレベルの記録を突破しなければ、代表になれないという厳しさです。
そんな中、北島康介選手が、100mと200mの平泳ぎで、見事1位を獲得し、4回連続のオリンピック出場を決めました。ほんとうにすごいです。3回連続の2競技金メダル獲得に、いやがおうにも期待が高まってしまいます。
北島選手のコーチを長年務め、現在は競泳の代表コーチを務める平井コーチを特集した番組が、北京オリンピック後に放映されました。その番組で平井コーチは、「競泳をする子は真面目な子が多い」と語っていました。
確かに、競泳の練習はほんとうに地味です。同じところを往復するだけで、髪はキャップの中に、目はゴーグルで隠れてしまいます。いくら派手な水着を着ても、泳いでいる間は、誰もそんなものに目もくれません。
そんな地道な努力を続け、照準を合わせた「その一瞬」に力を発揮できる心の強さと集中力を持った選手が、選ばれるのでしょう。
今回のオリンピックも、日頃から地道な努力を続け、さらに過酷な選考を勝ち抜いてきた精鋭たちに、期待したいものです。
ただし、「ポセイドン・ジャパン」という意味不明なキャッチフレーズだけは、どうしてもいただけません。ポセイドンには、どう考えても、プールは狭すぎでしょう。。。
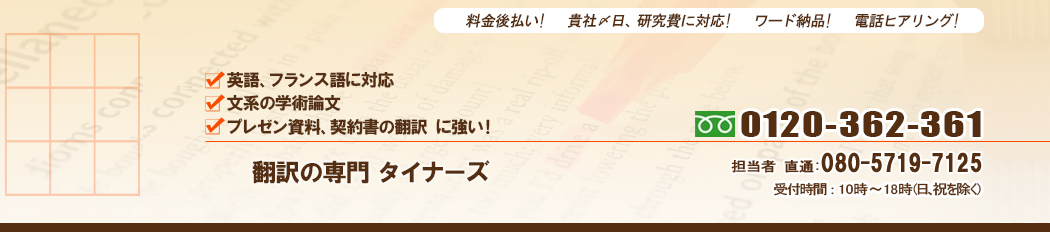 翻訳会社 タイナーズのブログ
翻訳会社 タイナーズのブログ